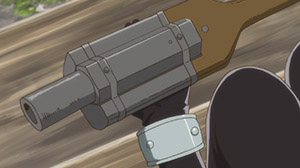LIBER VI SUB ROSA
―第六話 薔薇の下で― より

LIBER II CONTRA MUNDUM
―第二話 世界に対す― より
中世における帽子
中世に限らずだが、帽子には頭部に保護や防寒以外にも、身分や階級を表すための装いとしての役割をもってきた歴史がある。15世紀ではゴシック文化の成熟が進み、身分の高い女性が被っていたヘッドドレスである高い円錐形のエナン帽や、フードの先が筒状になったリリーパイプなどの現代から見れば奇妙なデザインの頭を飾る装いがあった。この作品でもル・メ伯ギヨームが、シャペロンという頭巾のようなもので頭を覆っているが、これはブルゴーニュから始まった当時の流行であった。このシャペロンを含め、黒を基調にしたル・メ伯の衣装は、当時としては結構ハイセンスなのである。